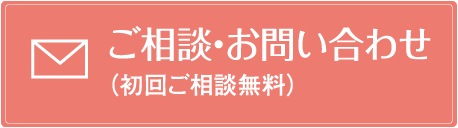障害年金の受給資格を得るための3つの要件
初診日- はじめてお医者さんにかかった日 -
初診日に厚生年金に加入していれば(通常、会社に勤めていれば)障害厚生年金の対象となります。
初診日に国民年金に加入していれば(自営業や主婦等)障害基礎年金の対象となります。
つまり、どの障害年金が対象になるかは初診日により決定しますので、非常に大切な要素になります。
保険料納付要件- キチンと年金保険料を納めているか -
年金は保険です。つまり納めていないと受け取れません。
初診日時点での判断となりますので、怪我や病気になってから納めても間に合いません。
障害状態要件- 障害認定基準に該当しているか -
怪我や病気の状態には認定基準があります。この認定基準に該当しなければいけません。
| 支給要件 |
1. 国民年金に加入している間に初診日があること 2. 保険料納付要件 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 3. 一定の障害の状態にあること |
|---|---|
| 障害認定時 | 初めて医師の診療を受けたときから(初診日)、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 ※ただし、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。 1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日(2級) 2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日(3級) 3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日(3級) 4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日(3級) 5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日(3級) 6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日) 7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日(2級) 8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日(3級) |
| 支給要件 |
1. 厚生年金に加入している間に初診日があること 2. 保険料納付要件 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 3. 一定の障害の状態にあること |
|---|---|
| 障害認定時 | ★障害基礎年金と同じ。 |
●障害年金の等級
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)の基準が定められています。 ※身体障害者手帳の等級とは異なります。
| 法律による定義 | 具体的には | |
| 1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 他人の介助を受けなければ日常生活のことが、ほとんど出来ないほどの障害の状態です。 身の回りのことはかろうじて出来るものの、それ以上の活動は出来ない方(または行うことを制限されている方)。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。 |
| 2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが出来ないほどの障害です。 家庭内で軽食を作るなどの軽い活動は出来ても、それ以上の重い活動は出来ない方(または行うことを制限されている方)。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が 2 級に相当します。 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの | 労働が著しい制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とするような状態です。 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。 |
| 障害手当金 | 「傷病が治ったもの」で、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの | 初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)もので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った方が障害手当金に相当します。 |